2026年1月9日、金曜ロードショーでスタジオジブリの映画『かぐや姫の物語』が放送されました。息をのむほどの美しい映像と、心を締め付けるような物語に、多くの人が再び魅了されたことでしょう。しかし、鑑賞後に残るのは、単純な「感動」という言葉だけでは片付けられない、不思議な感覚ではなかったでしょうか。
特に、物語のクライマックス。月に帰るかぐや姫と地上に残される人々との別れのシーン。月の使者たちが奏でる音楽の不気味さ、そして、羽衣をまとった瞬間に地球での記憶をすべて失い、それでもなお故郷の星を振り返るかぐや姫のあの表情……。胸にぽっかりと穴が空いたような虚無感と、どうしようもない切なさが入り混じった、複雑な感情に包まれた方も少なくないはずです。その感覚をうまく言葉にできず、もどかしい思いを抱えているかもしれません。
インターネット上では、この作品に対する評価は大きく二分されています。「紛れもない傑作だ」と絶賛する声がある一方で、「ストーリーが暗すぎる」「後味が悪い」といった批判的な意見も根強く存在します。なぜ、これほどまでに評価が分かれるのでしょうか。そして、私たちの心をこれほどまでに揺さぶり、虚無感さえもたらすこの物語の正体とは、一体何なのでしょうか。
この記事では、公式情報やメディアの分析、そしてSNS上に溢れる無数の口コミを徹底的に調査し、『かぐや姫の物語』が投げかける深い問いと、その魅力の核心に迫ります。あらすじや登場人物の行動の裏に隠された意味、賛否両論が巻き起こる理由、そして多くの人が抱くあの不思議な感情の源を、あらゆる角度から解き明かしていきます。この記事を読み終える頃には、あなたが抱いた言葉にできない感情の輪郭が、きっと鮮明になっているはずです。
物語の核心へ:『かぐや姫の物語』あらすじとネタバレ解説
物語の深層を探る前に、まずはその骨格となる物語を振り返っておきましょう。高畑勲監督が8年の歳月と51.5億円もの巨額の制作費を投じて創り上げたこの作品は、誰もが知る日本最古の物語『竹取物語』を原作としながらも、独自の解釈と圧倒的な表現力で、まったく新しい生命を吹き込んでいます。
竹の中から現れた、手のひらサイズの姫
物語は、竹取の翁が光り輝く竹の中から小さな姫君を見つける、幻想的な場面から始まります。翁と媼は、この不思議な赤子を「姫」と名付け、自分たちの子供として愛情を注ぎ育てます。姫は驚くべき速さで成長し、周囲の子供たちからは「タケノコ」と呼ばれ、豊かな自然の中で生命力いっぱいに駆け回ります。この時期、彼女は捨丸という少年と出会い、淡い恋心を抱きます。鳥や獣、草花と共に生きるこの日々は、彼女にとって「生」の喜びに満ちた、かけがえのない時間でした。
都での暮らしと失われた自由
しかし、翁が竹の中から黄金や美しい衣を見つけるようになったことで、彼女の運命は大きく変わります。翁は「姫を高貴な身分に育て上げることこそが天命だ」と信じ、都に壮大な屋敷を建て、姫を移り住まわせます。姫は「かぐや姫」という名前を授かり、高貴な姫君としての作法や教養を叩き込まれます。しかし、それは同時に、彼女が愛した野山での自由な生活を奪われることを意味していました。窮屈な暮らしの中で、彼女の心は次第に色を失っていきます。
やがて、かぐや姫の美貌は都中の評判となり、5人の貴公子たちが次々と求婚に訪れます。彼らはかぐや姫を「この世のものとは思えない宝物」としてしか見ておらず、その心に寄り添おうとはしません。かぐや姫は、彼らに到底手に入らないであろう「伝説の宝物」を持ってくるよう難題を突きつけ、求婚を退けます。ついには、国の最高権力者である帝までもが彼女を求めますが、かぐや姫は彼の求愛をも拒絶します。
犯した罪と罰、そして月の迎え
誰にも心を理解されず、富や権力によって自分の価値を決めつけられる日々に絶望したかぐや姫は、心の叫びをあげます。「こんな場所からいなくなりたい」と。その願いは、彼女がかつていた場所、月へと届いてしまいます。実は、かぐや姫は罪を犯し、その罰として地球に送られてきた月の民だったのです。地球での生活は、彼女にとって「罰」であると同時に、生きる喜びを味わうための時間でもありました。しかし、地球を穢れた場所とみなし、そこでの記憶を消し去ることが救いだと信じる月の使者たちが、彼女を迎えに来る日が近づいていました。
自分の本当の居場所がここではないと悟ったかぐや姫は、最後に一目だけでもと、かつて心を通わせた捨丸に会いに行きます。捨丸は既に妻子を持っていましたが、かぐや姫への想いを断ち切れてはいませんでした。二人は再会し、かつてのように野山を駆け巡る夢を見ますが、それも束の間の幻でした。
そして、運命の夜。月の使者たちの一団が、きらびやかで、しかしどこか不気味な音楽と共に天から降りてきます。翁と媼、そして彼らを守ろうとする者たちの抵抗もむなしく、かぐや姫は使者たちの前に引き出されます。彼女は地球での喜び、悲しみ、そして愛情を涙ながらに訴えますが、使者の一人が無慈悲に「羽衣」を彼女の肩にかけます。その瞬間、かぐや姫の目から光が消え、地球でのすべての記憶が失われてしまうのです。記憶をなくしたかぐや姫は、月の行列に加わり、昇天していきます。そして、遠ざかる地球を、何も思い出せないはずなのに、一筋の涙を浮かべながら、ただ静かに見つめるのでした。
なぜ私たちは心を奪われるのか?圧倒的な映像美と「余白」の芸術
『かぐや姫の物語』を語る上で、その唯一無二の映像表現を避けて通ることはできません。制作期間8年、総作画枚数17万枚という数字もさることながら、この作品が観る者に与える視覚的な衝撃は、従来のセル画アニメーションとは一線を画します。
水彩画が動き出す、スケッチ風描画の革新性
最大の特徴は、淡い色彩で描かれた水彩画のようなタッチです。高畑勲監督と美術監督の男鹿和雄氏は、あえて細部を描き込まず、大胆な筆致と「余白」を活かしたスケッチ風の描画スタイルを追求しました。これは、すべてを緻密に描き込むことでリアリティを追求する現代のアニメーションの潮流とは真逆のアプローチです。
高畑監督は、この手法について「観客の想像力を喚起するため」だと語っています。細部まで描き込まれた絵は、それだけで完結してしまい、観る者の想像が入り込む隙間がありません。しかし、『かぐや姫の物語』の画面は、意図的に情報が「抜かれて」います。その余白があるからこそ、私たちは無意識のうちに、自身の記憶や経験を投影し、描かれていない背景や人物の感情を補完しようとします。かぐや姫が野山を疾走するシーンの躍動感、都の暮らしの息苦しさ、それらが私たちの心に直接訴えかけてくるのは、この「余白の力」に他なりません。
特に、かぐや姫が偽りの宴から逃げ出し、狂ったように都を疾走するシーンは圧巻です。背景は荒々しい墨の線と化し、かぐや姫自身の輪郭さえも崩れ、彼女の心の叫びそのものが画面に叩きつけられます。これは、アニメーションという枠を超えた、一つの芸術表現の高みと言えるでしょう。
51.5億円の赤字覚悟で貫いた「本物」への執念
この革新的な映像表現は、しかし、商業的には大きなリスクを伴うものでした。制作費は最終的に51.5億円にまで膨れ上がり、興行収入24.7億円という結果は、約27億円もの大赤字を意味しました。なぜ、これほどのコストをかけてまで、高畑監督はこの表現にこだわったのでしょうか。
それは、彼が「本物」の感情を描きたかったからです。キャラクターの動き一つひとつ、背景の草木一本一本に「実感」を込める。そのためには、従来の分業制アニメーションの効率的な作り方では不可能でした。1カットずつ、監督、作画設計の田辺修氏、美術監督の男鹿和雄氏が確認し、納得がいくまで修正を繰り返すという、途方もない時間と労力が費やされたのです。
この商業性を度外視したとも言える芸術への執念こそが、『かぐや姫の物語』を単なるアニメーション映画ではない、特別な作品へと昇華させているのです。興行的な成功だけが作品の価値を決定するものではない。この映画は、その事実を静かに、しかし力強く物語っています。
賛否両論の嵐:なぜ『かぐや姫の物語』の評価は二分するのか?
これほどの芸術性を持ちながら、『かぐや姫の物語』の評価は、公開当初から現在に至るまで、賛否両論に大きく分かれています。この評価の分裂こそが、この作品の複雑さと深さを象徴していると言えるでしょう。ここでは、なぜ評価が二分するのか、その理由を多角的に分析します。
「傑作だ」と絶賛する声:表現の深さに魅了される人々
まず、肯定的な評価の多くは、前述した圧倒的な映像表現とその芸術性に向けられています。水彩画のようなタッチ、余白を活かした構図、そして感情の爆発をそのまま描き出したかのような作画は、「アニメーションの新たな地平を切り開いた」と高く評価されています。これらの人々は、物語の筋書きだけでなく、その「表現」そのものに価値を見出し、深い感動を覚えています。
また、物語が持つ感情的な深さも絶賛の理由です。生きる喜びに満ちた幼少期から、自由を奪われ苦悩する都での生活、そして抗えない運命に翻弄されるラストまで、かぐや姫が経験する感情の振れ幅は非常に大きい。その喜びも悲しみも、ごまかしなく描き切ることで、観る者の心に強く訴えかけます。特にラストシーンがもたらす、感動と虚無感が入り混じった複雑なカタルシスは、他の作品では味わえない唯一無二の体験として、多くの人の心に刻まれています。
「よくわからなかった」という声:ストーリー偏重の現代が浮き彫りに
一方で、批判的、あるいは戸惑いの声も少なくありません。その中心にあるのが、「ストーリーが暗い」「救いがない」「後味が悪い」といった感想です。
スタジオジブリのプロデューサーである鈴木敏夫氏は、この現象について興味深い分析をしています。彼は、映画公開後、特に若い世代から「何だ、月へ帰っちゃうのか」という、物語の結末だけを追った単純な感想が多く寄せられたことにショックを受けたと語っています。これは、現代の観客、特に若者層が、作品の「表現」よりも「ストーリーの筋書き」や「結末の意外性」を重視する傾向にあることを示唆しています。
「現代は、どう表現しているのかがすっ飛んでしまって、お話の複雑さのほうにだけ感心が向いている、そんな時代なんだなということを、改めて思い知らされました。」(鈴木敏夫『仕事道楽 新版』より)
確かに、近年の映画の宣伝文句には「あなたは最後に騙される」といった、ストーリーのどんでん返しを煽るものが目立ちます。こうした風潮の中で育った世代にとって、『かぐや姫の物語』のような、結末が既知であり、表現の機微を味わうことに重きを置いた作品は、退屈で分かりにくいものに映ってしまうのかもしれません。2015年の初回放送時に18.2%だった視聴率が、2026年の放送では4.9%にまで低下している事実も、この世代間の価値観の変化を裏付けている可能性があります。
感情移入を拒む登場人物たち
さらに、登場人物たちの行動が、単純な善悪で割り切れず、感情移入を難しくしている点も、評価が分かれる一因です。
- 翁と媼: 当初は愛情深い親として描かれますが、翁は次第に富と名声に目がくらみ、かぐや姫の幸せよりも世間体を優先するようになります。これは娘を想う親心のエゴイズムであり、多くの人が共感しつつも、完全には肯定できない複雑な感情を抱かせます。
- 捨丸: かぐや姫の初恋の相手でありながら、彼女が都へ去った後、別の女性と結婚し子供も儲けています。それにもかかわらず、再会したかぐや姫と共に逃げようとする彼の姿は、「妻子捨丸」とSNSで揶揄されるなど、無責任で自己中心的な行動として多くの批判を集めました。しかし、それは同時に、抗えない運命や過去の想いに揺れる人間の弱さの表れでもあり、物語に深みを与えています。
- 帝: 最高の権力者でありながら、かぐや姫の心を力で支配しようとする傲慢な人物として描かれます。「私がこうすることで喜ばぬ女はいなかった」という台詞は、彼の自己中心性を象徴していますが、同時に、本当に欲しいものは決して手に入らないという権力者の孤独をも感じさせます。
これらの登場人物たちは、決して完璧な善人でも、完全な悪人でもありません。誰もがエゴや弱さを抱えた「人間」として描かれているからこそ、観る者は安易な感情移入を許されず、物語に対して複雑な距離感を持つことになるのです。
ラストシーン徹底考察:なぜ虚無感と感動が同時に押し寄せるのか?
物語のクライマックス、月の使者がかぐや姫を迎えに来る一連のシーンは、この映画のテーマが最も凝縮された、最も謎に満ちた場面です。多くの人が抱く「虚無感」と「感動」が入り混じった感情は、まさにこのシーンから生まれています。
死のメタファーとしての「月の迎え」
天から降りてくる月の使者たちの一団。彼らは仏教における来迎図(臨終の際に阿弥陀如来が迎えに来る様子を描いた図)を彷彿とさせますが、その表情は一切なく、奏でる音楽は陽気でありながら、どこか空虚で不気味です。彼らは地上を「穢れた場所」と断じ、かぐや姫の訴えにも一切耳を貸しません。この姿は、抗うことのできない「死」そのもののメタファーとして解釈できます。
地上の人々がどれだけ嘆き悲しんでも、死は訪れる。そして、死後の世界(月)から見れば、現世(地球)の喜びや悲しみは、すべて消し去るべき「穢れ」でしかないのかもしれない。この圧倒的で無慈悲な運命を前に、私たちは無力感と虚無感を覚えるのです。
「羽衣」が消し去る記憶と「生」の肯定
そして、最も衝撃的なのが、羽衣をまとったかぐや姫が地球での記憶をすべて失ってしまう場面です。月の使者にとって、これはかぐや姫を苦しみから解放する「救済」の儀式です。しかし、私たち観客は、彼女が野山を駆け回り、笑い、泣き、恋をした、かけがえのない時間のすべてを知っています。その「生」の輝きが、一瞬にして無に帰してしまうことへの、どうしようもない喪失感と怒りを感じずにはいられません。
高畑監督は、この物語を「姫の犯した罪と罰」というテーマで描きました。かぐや姫が月で犯した罪とは、「地球への憧れ」でした。そして、その罰として地球に送られ、生の喜びと苦しみを存分に味わう。しかし、皮肉なことに、その「生」の記憶こそが、月に帰る際には消し去られてしまうのです。これは、生きることそのものが持つ、根源的な矛盾と悲しみを突きつけてきます。
記憶を失ってもなお、地球を振り返る最後の涙
しかし、物語は完全な絶望では終わりません。すべての記憶を失ったはずのかぐや姫は、遠ざかっていく地球を振り返り、その瞳から一筋の涙をこぼします。なぜ、彼女は涙を流したのでしょうか。
これは、頭(記憶)では忘れてしまっても、心と身体が地球での「生」の輝きを覚えていたからではないでしょうか。月の世界の静かで永遠の「無」よりも、喜びも悲しみもある、不完全で儚い地球での「生」こそが、本当に価値のあるものだった。その無意識の叫びが、あの最後の涙に凝縮されているのです。
記憶は消されても、生きたという事実は消えない。この最後のシーンは、完全な虚無の中にかすかな光を灯し、「生きること」そのものを力強く肯定しています。だからこそ私たちは、深い虚無感と共に、どうしようもないほどの感動を覚えるのです。それは、この物語が、私たち自身の人生そのものを映し出しているからに他なりません。
まとめ:『かぐや姫の物語』が私たちに遺したもの
『かぐや姫の物語』は、単なる古典の焼き直しではありません。それは、高畑勲という一人の偉大な芸術家が、人生の最後に私たちに遺した、壮大な問いかけです。
圧倒的な映像美と革新的な表現で、「生きること」の輝きと、それに伴う痛みを真正面から描き切ったこの作品。その評価が賛否に分かれるのは、この物語が、観る者自身の人生観や価値観を揺さぶり、安易な答えを与えてくれないからです。ストーリーの結末だけを追うのではなく、その表現の奥にあるもの、登場人物たちの心の機微に触れたとき、私たちは初めてこの物語の真価に気づくのかもしれません。
ラストシーンで感じたあの虚無感は、人生の儚さと抗えない運命への絶望かもしれません。しかし、同時に感じたあの感動は、それでもなお「生きることは素晴らしい」という、魂からの叫びだったのではないでしょうか。
『かぐや姫の物語』は、観るたびに新しい発見と問いを与えてくれる、底知れぬ深みを持った作品です。もしあなたが、鑑賞後に言葉にできない感情を抱いたのなら、それはこの作品があなたの心の奥深くに届いた証拠です。ぜひ、時間を置いて何度もこの物語に触れてみてください。そのたびに、かぐや姫が地球で見たのと同じ、かけがえのない「生」の輝きを、あなた自身の人生の中に見出すことができるはずです。


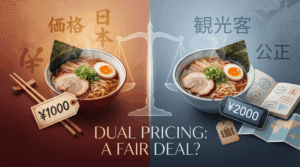







コメント