はじめに:なぜ、命を守る「駆除」が止まったのか
北海道の積丹町で発生した、町議会議員と地元猟友会との間のトラブルは、一地方自治体の小さな出来事として片付けられない、日本の地方行政が抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。この事件は、単なる感情的な対立ではなく、町民の生命と安全に直結する危機管理の機能不全を示しています。
読者の皆様がこの記事にたどり着いたのは、「なぜ一町議の暴言で町全体の安全が脅かされるのか」「なぜ町議会や町長は問題解決に動かないのか」という、根源的な疑問と不安を抱えているからでしょう。
この記事では、このトラブルの核心を多角的に分析し、読者の皆様の疑問を解決するとともに、この問題が示唆する地方自治のあり方について、建設的な視点から考察します。
第1章:トラブルの核心と「謝罪なき釈明」の検証
事件は2025年9月27日、積丹町で体重284kgの大型ヒグマが箱罠にかかった際に発生しました。現場で駆除作業にあたっていた猟友会のハンターが、近くにいた町議会議員に対し、安全確保のために離れるよう注意したところ、町議が激高し、ハンターに対して威圧的な発言をしたとされています。
1.1. 暴言の内容と猟友会の「怒り」
関係者の証言によると、町議はハンターに対し、駆除作業の人数や報償金に言及しつつ、最終的に「俺にそんなことするなら駆除もさせないようにするし、議会で予算も減らすからな。辞めさせてやる」といった趣旨の言葉を浴びせたと報じられています。
命がけで作業にあたるハンターにとって、この発言は職務に対する侮辱であり、公職にある者による職権の濫用を示唆する恫喝に他なりません。このため、地元猟友会は町に対し、全会一致で出動拒否を伝え、町民の安全確保という最優先の行政サービスが停止する事態に発展しました。
1.2. 町議の「謝罪なき釈明」の論理的破綻
一方、町議は報道機関の取材に対し、「『辞めさせてやる』とは言っていない」と暴言の一部を否定しつつ、「一町議がそんな力を持っているわけがない」と釈明しました。
皆様が最も気になっているのは、この「一町議がそんな権限を持っている訳がない」という発言でしょう。この釈明は、法的・論理的に以下のような問題を抱えています。
| 観点 | 町議の主張 | 検証結果と問題点 |
| 権限の有無 | 「一町議にそんな権限はない」 | 事実:一町議単独で予算を減らしたり、猟友会との契約を解除したりする法的権限はない(地方自治法)。 |
| 発言の性質 | 権限がないから問題ない | 問題:発言は権限の有無に関わらず、公務遂行中の専門職に対する威圧行為であり、公職者としての品位の保持義務に反する。 |
| 謝罪の有無 | 発言を否定し、謝罪しない | 問題:暴言の一部を否定しても、「何で急に撃つんだ」「こんなに人数いるのか」といった威圧的な言動自体は認めている。この言動が猟友会を激怒させ、行政サービス停止という重大な結果を招いたことに対する道義的・政治的責任は極めて重い。 |
| 読者の疑問 | 責任逃れではないか? | 結論:権限がないことを理由に謝罪を拒否する姿勢は、自らの言動が引き起こした結果に対する責任を回避しようとするものと見なされざるを得ません。 |
町議の釈明は、「法的権限がないこと」を盾に、「公職者としての道義的・政治的責任」から逃れようとするものと解釈できます。しかし、この言動が町民の安全という最優先事項を停止させた事実は、権限の有無を超えて、公職者として最も問われるべき点です。
第2章:猟友会依存の限界と行政の構造的問題
なぜ、一地方議会議員の発言が、町全体のクマ対策を麻痺させるほどの力を持ったのでしょうか。それは、日本の地方自治体における有害鳥獣駆除体制の構造的な脆弱性に起因します。
2.1. 猟友会は「行政の代行者」
多くの地方自治体、特に積丹町のような過疎地域において、クマやシカなどの有害鳥獣駆除は、地元の猟友会に業務委託されています。これは、専門的な知識、技能、そして猟銃の所持許可を持つ人材が、行政内部にほとんど存在しないためです。
| 駆除体制の現状 | 詳細 |
| 主体 | 地方自治体(町長)が鳥獣保護管理法に基づき許可 |
| 実働部隊 | 地元の猟友会(ボランティア的側面を持つ業務委託) |
| 課題 | 猟友会の高齢化と担い手不足が深刻化。行政の依頼を断れない状況が常態化し、行政への依存度が高い。 |
猟友会は、ボランティア的な使命感と、自治体からの報償金によって、町民の安全を文字通り命がけで守ってきました。今回のトラブルは、この「行政の代行者」である猟友会の尊厳を傷つけ、長年の信頼関係を一瞬で崩壊させたことに、問題の根深さがあります。
2.2. 町長・町議会が「中途半端なまま放置」する理由
読者の皆様の最大の疑問の一つは、「なぜ町長や町議会は、この重大な事態を中途半端なまま放置しているのか」という点でしょう。この「放置」の背景には、以下の行政特有の事情が絡み合っています。
2.2.1. 行政の「保身」と「情報共有の欠如」
積丹町は、猟友会が出動拒否という重大な事態に陥っていることを、町民や議会に速やかに伝えていませんでした。町は「事実関係の把握に時間がかかり、議会に報告すべきか判断に迷った」と釈明していますが、これは危機管理における初動対応の失敗であり、行政の透明性と説明責任の観点から強く批判されるべきです。
•危機管理の鉄則: 町民の生命に関わる情報は、事実関係が不明確であっても、リスク情報として速やかに公開し、注意喚起と対応状況を共有する必要があります。
•「判断に迷った」の真意: この発言は、問題を表沙汰にすることで生じる行政への批判や責任追及を恐れた「保身」の姿勢と見なされても仕方ありません。
2.2.2. 地方議会の「身内意識」と「機能不全」
町議会がこの問題を解決できない背景には、**「身内意識」と「議会の機能不全」**が指摘されます。
1.議員の資質を問う難しさ: 地方議会では、議員同士の人間関係が密接であるため、同僚議員の不祥事に対し、厳正な倫理的責任を追及する動きが鈍くなる傾向があります。
2.町長と議会の関係: 町長と議会は、本来、緊張関係にあるべきですが、地方では馴れ合いや相互依存の関係になりがちです。町長が問題解決に消極的である場合、議会側も町長を強く追及し、問題解決を迫る動機が弱まることがあります。
この結果、町民の安全という最優先事項よりも、行政内部の人間関係や保身が優先され、問題が長期化していると見ることができます。
第3章:地方議員の倫理と「田舎のおじいちゃん」が持つべき責任
質問者は、「田舎のおじいちゃん達は、問題解決して猟友会の人たちに出動して貰えるように働きかける努力する気はないのでしょうか?」と、地方政治の停滞に対する強い憤りを表明しています。この感情は、多くの町民が共有するものでしょう。
3.1. 地方議員の倫理規定と懲罰
地方議員は、地域住民の代表として、高い倫理観と品位が求められます。多くの自治体では、政治倫理条例を定め、議員の行動規範を規定しています。
今回の積丹町議の発言は、公務遂行中の専門職に対するハラスメントであり、職権を背景とした威圧です。これは、地方議員が守るべき品位の保持義務に明らかに反する行為であり、議会は懲罰動議を提出し、議員の責任を明確にすべき事案です。
•懲罰動議の役割: 懲罰は、議員個人の過ちを正すだけでなく、議会全体が公職者としての倫理を重んじていることを町民に示す、重要な意思表示となります。
3.2. 危機管理における町長の「リーダーシップ」の欠如
地方自治体の長である町長は、町民の生命と財産を守る最終責任者です。猟友会が出動拒否している状況は、町長が直ちに解決すべき危機管理上の最優先課題です。
町長が取るべき行動は、以下の3点に集約されます。
1.行政の代表としての謝罪: 町議の個人的な謝罪とは別に、町長は行政の長として、猟友会に対し、これまでの敬意の欠如と今回の事態を招いたことへの誠意ある謝罪を行うべきです。
2.迅速な仲裁と関係修復: 猟友会との正式な協議の場を設け、駆除活動に対する正当な評価と、活動条件の改善を約束するなど、信頼回復に向けた具体的な努力を示すべきです。
3.代替体制の構築: 短期的に他地域の猟友会や警察との連携を強化しつつ、中長期的にはガバメントハンター(自治体職員のハンター)の育成など、猟友会に過度に依存しない持続可能な駆除体制の構築に着手するリーダーシップを示すべきです。
「田舎のおじいちゃん」と揶揄されるかもしれない地方のリーダーたちこそ、今、町民の安全を守るという使命に基づき、迅速かつ建設的な行動を示すことが求められています。
第4章:問題解決への建設的な提言
この積丹町の事例は、他の自治体にとっても教訓となるべきです。問題解決と再発防止のために、以下の提言を行います。
4.1. 猟友会との「対等なパートナーシップ」の確立
地方自治体は、猟友会を単なる「駆除の実行部隊」としてではなく、町民の安全を守るための対等なパートナーとして扱うべきです。
| 現状の課題 | 建設的な解決策 |
| 活動への敬意の欠如 | 駆除活動の危険性と専門性を正当に評価し、感謝と敬意を行動で示す。 |
| 報償金・活動条件の不満 | 報償金の適正化、装備品の提供、保険制度の充実など、活動環境の改善を協議する。 |
| 連携不足 | 警察、消防、行政、猟友会が参加する定期的な合同訓練・情報共有会議を義務化する。 |
4.2. 地方議会における倫理規定の厳格化と研修
地方議員によるハラスメントや威圧行為は、行政の士気を下げ、結果的に町民サービスを低下させます。
•倫理規定の強化: 政治倫理条例に、職員や業務委託先に対するハラスメント・威圧行為を明確に禁止する条項を追加し、違反者には厳格な罰則(例えば、一定期間の議員報酬の停止など)を設けるべきです。
•倫理研修の義務化: 地方議員に対し、ハラスメント防止や危機管理、地方自治法における権限の範囲に関する研修を義務付け、公職者としての自覚を促すべきです。
4.3. 危機管理体制の多角化と行政の主体性
猟友会が出動拒否した際の代替手段を持たないことは、危機管理上の最大の欠陥です。
•ガバメントハンターの育成: 猟友会への依存度を下げるため、自治体職員の中から狩猟免許取得者を増やし、公的な駆除専門チームを組織する。これは、中長期的な安定供給策となります。
•広域連携の強化: 近隣自治体の猟友会や、都道府県の猟友会連合会との間で、緊急時の相互協力協定を締結し、リスクを分散させるべきです。
結論:町民の安全を取り戻すために
積丹町のトラブルは、**「一町議の暴言」という個人の問題に留まらず、「猟友会依存」という構造的な問題と、「行政の保身」**という危機管理の問題が複合的に絡み合った結果です。
皆様の「一番気になるところ」である**「なぜ解決しないのか」という問いへの答えは、「行政の長と議会が、町民の安全という最優先事項よりも、内部の人間関係や責任回避を優先しているから」**に尽きます。
しかし、この問題は解決可能です。町長が行政の代表として誠意をもって謝罪し、議会が自浄作用を発揮して議員の倫理的責任を追及すること。そして、猟友会との対等なパートナーシップを再構築し、持続可能なクマ対策の体制を整えること。
積丹町が、この危機を乗り越え、町民の安全を最優先する、真に機能する地方自治を取り戻すことを心から願っています。
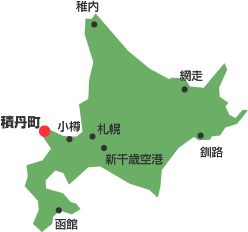

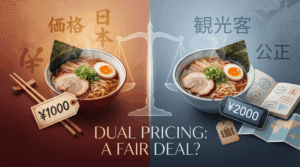






コメント